学会情報
学会は情報収集の場

様々な学術講演に積極的に参加をしています。
現代の社会は高齢化であったり、食生活の変化など急速な変化が起こっています。
歯科の治療も、医科との連携などが積極的に行われ、時代の変化とともに進化を続けています。
そのような情報を少しでも多く、そして素早く取り入れるために学術的なイベントに参加をしています。
ここでは、どのような情報が交換されているのかを、簡単ではありますが紹介させて頂いております。
春季日本歯周病学会 令和7年5月23日〜24日

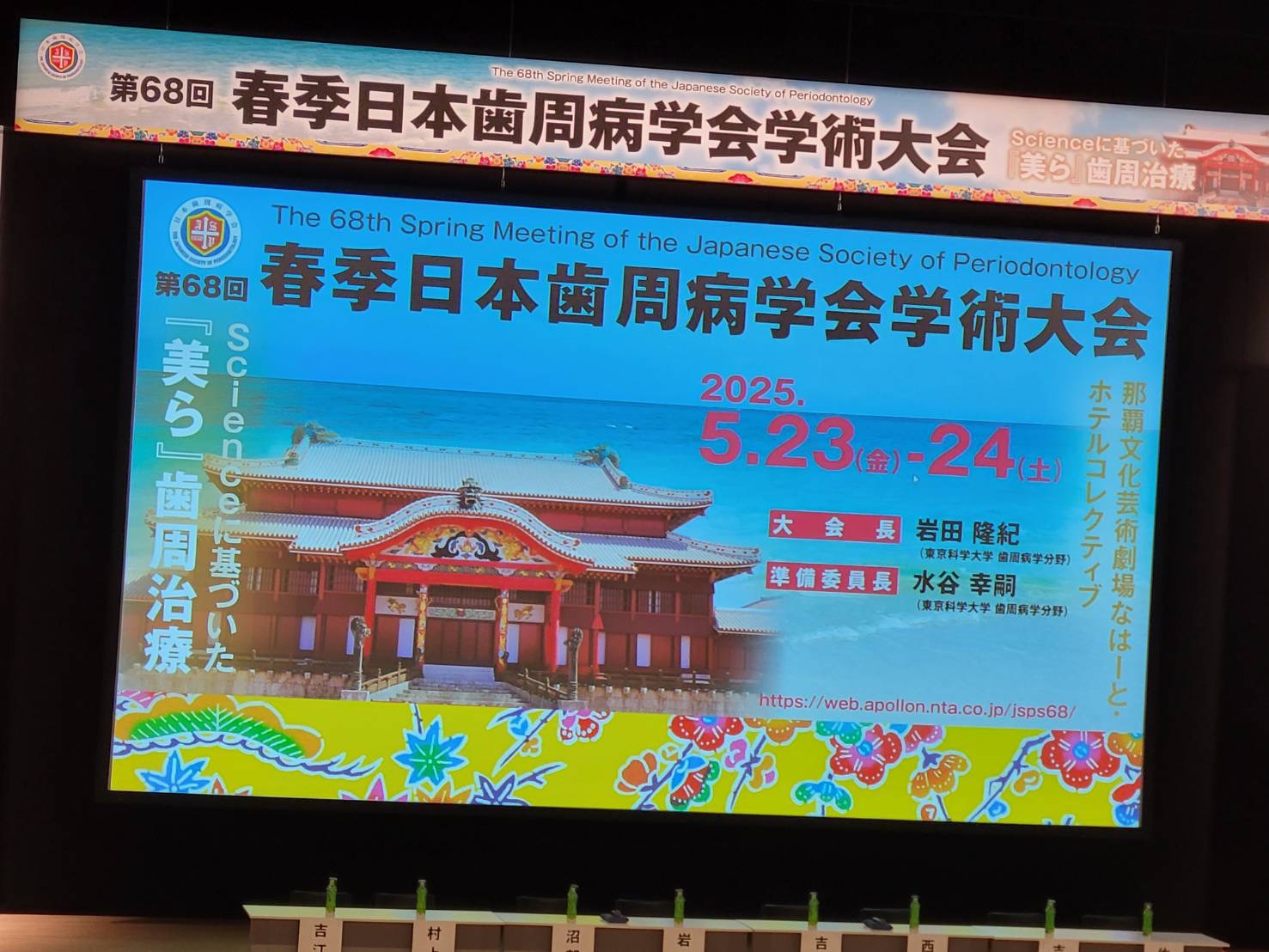
春季歯周病学会は沖縄県那覇市にて開催されました。
再生療法における効果や注意すべき点など、細かい部分に迫る発表が多く見られました。
再生療法は歯周病によって失われた歯周組織を再生させる目的で行われます。
再生治療を行えば100%元に戻ると思われている方もいらっしゃいますが、実際には30%〜80%です。
失った骨の量や患者さん自身の身体の状態によっても左右されます。
治療前に患者さんに対して行う説明の重要性についての議論も行われました。
当院におきましては、再生療法を以前より行ってきているため、患者さんへの説明はその当時から現在に至るまで時間を取って行っております。
秋季日本歯周病学会 令和6年10月4日〜5日

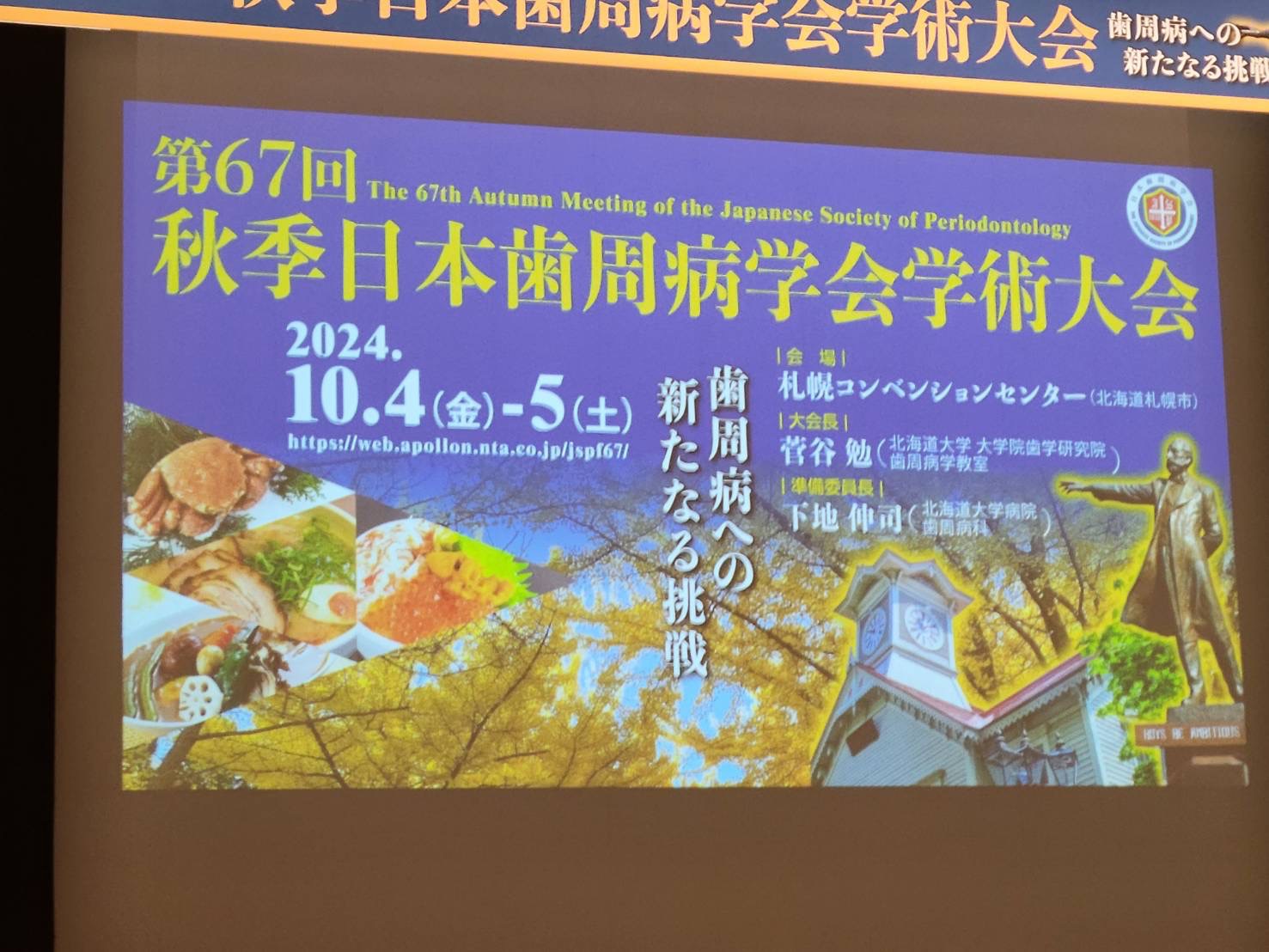
秋季歯周病学会は北海道札幌にて開催されました。
例年、歯周病によって溶けてしまった骨を再生する治療についての講演は多く見られました。
歯周病に罹患すると歯周病菌が発する毒素によって、歯を支える骨などいわゆる歯周組織を破壊することは既に認められています。
今回の学会では歯を支える骨を溶かすだけではなく、骨が欠けてしまう事例そしてそれをどう予防していくかという講演がありました。
幸いにも私の医院に来院される患者さんは歯周病に対する予防の意識が高いためかそのような事例はほとんど見受けられませんが、そのような事は起こり得るという意識を持って今後も治療に望む所存です。
秋季日本歯周病学会 令和5年10月13日


秋季歯周病学会は長崎の出島にて開催されました。
新しい歯周組織再生療法についての講演もありましたが、例年議題で上がる歯周病と全身疾患の関連性についての講演が印象深かったです。
歯周病は歯茎が腫れたり歯を支える骨が溶けていく疾患です。
その原因となるのは歯周病菌などの細菌で、その細菌が血管を通り身体の中で悪さをします。
歯周病を治療していくことで糖尿病や心疾患の症状が改善された報告例もあります。
また、ヤグレーザー装置を使用した歯周病治療についての講演もありました。
レーザー光線にはいくつかの種類がありますが、ヤグレーザーは優れた殺菌力を持っているため歯周病の原因菌を素早く除去することが可能とされています。
また、弱った歯茎にレーザーを当てることで歯茎の治癒能力を活性化させることもできます。
当院でも一早くこのレーザー装置を導入し、治療に役立てています。
最新の治療法から従来より確立されている治療など多くの講演を聞くことができ、歯周病治療の大切さを改めて感じた長崎の学会でした。
日本歯周病学会 令和5年5月26日

コロナ禍においてはリモート配信による学会も、今年度は通常通り現地での通常開催となりました。
今回は歯周病などによって失った歯を支える骨を再生する技術についての情報発信などがありました。
また、歯周病患者におけるコロナウィルス重症化リスクの話もありました。
リモートでの開催も新しい感覚と効率的な開催という意味では素晴らしい事と思いますが、現地に足を運び人と会って議論することはそれはそれで大切なことだと思います。
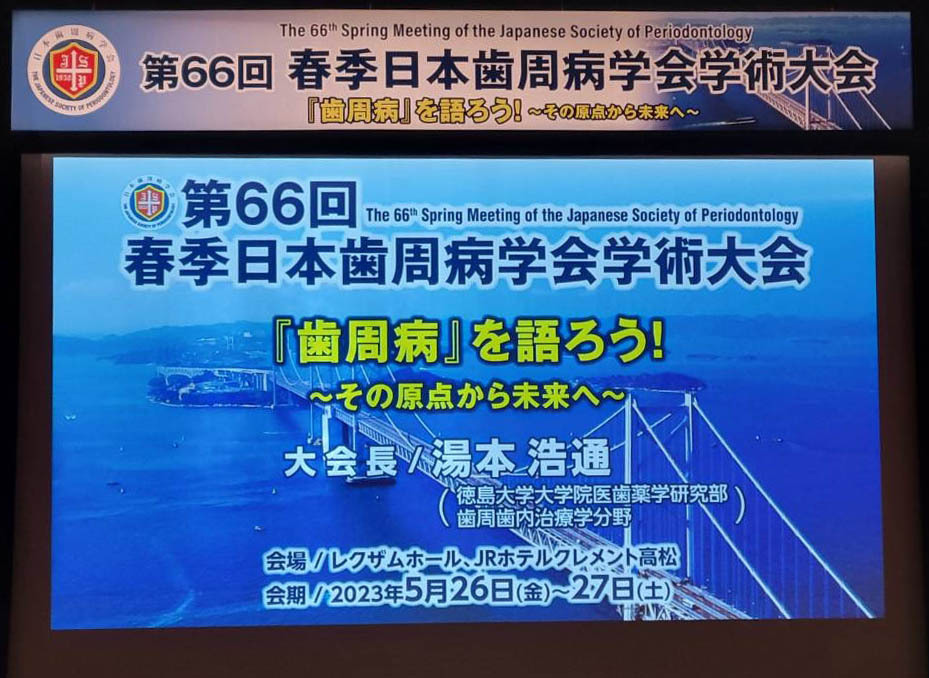
日本歯周病学会 平成29年12月16日

歯科の世界において、常日頃の研究は欠かせないものです。
今回の歯周病学会で、私が注目した研究は「歯周病の原因菌」についてで、身体に最も悪い影響を与える歯周病菌を突き止めた!
という内容でした。
歯周病は生活習慣病や心臓の疾患などとの関わりがあるとの研究が盛んに行われ、このような発見が今後も多くされることに期待感を持つことが出来た学会でした。
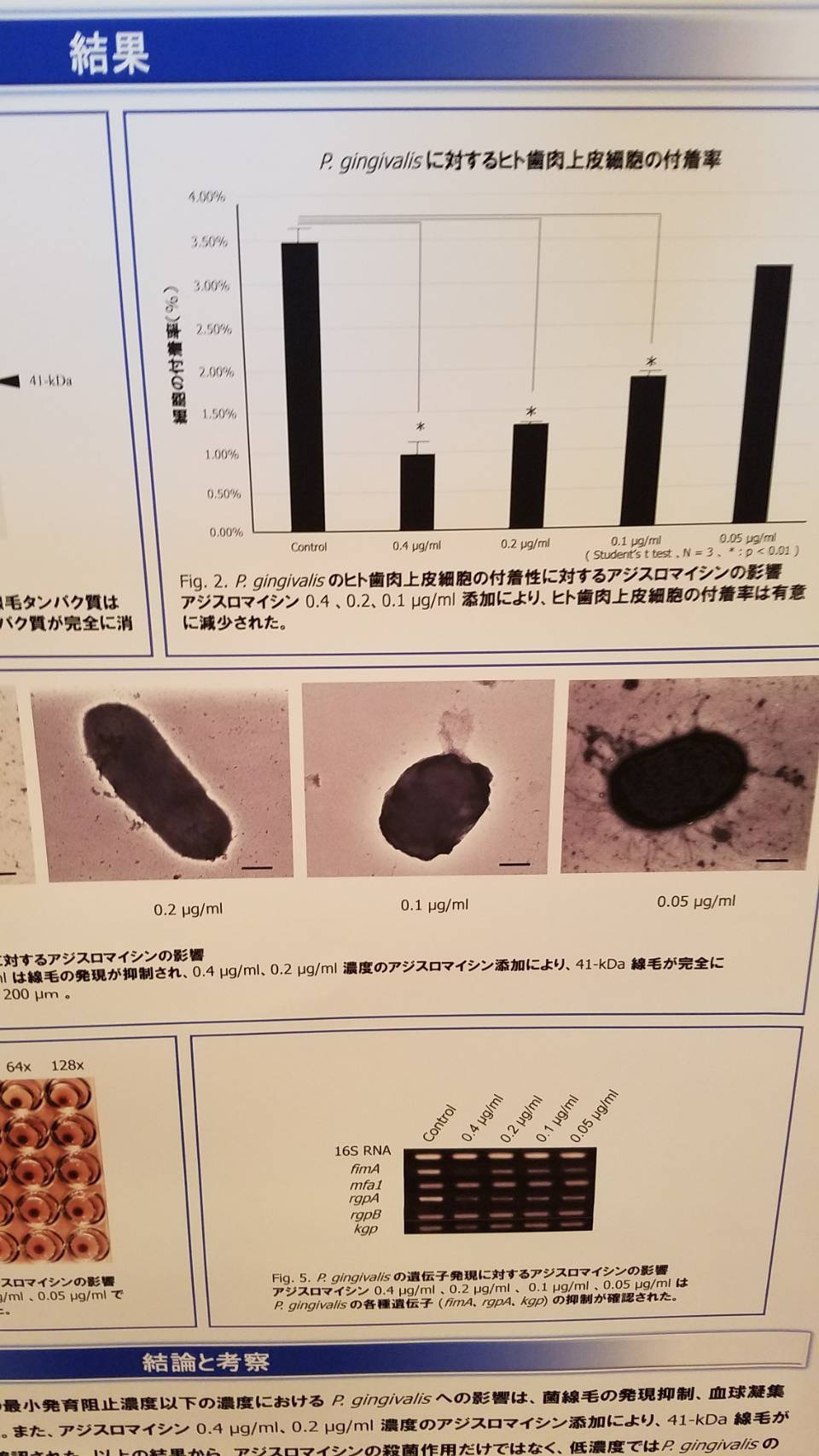
日本先進インプラント医療学会 平成29年3月26日

『超高齢化社会』できることなら目を背けたい言葉ですね。
しかしこれは日本が直面する大きな社会問題です。
歯科の世界では高齢化に伴い、歯周病などの対策に関する議論が多く交わされています。
私たちは目を背けることなく、高齢化に伴う口腔疾患を予防し、治療していくかを常に考えなくてはなりません。
国際歯科学士会 平成29年3月12日
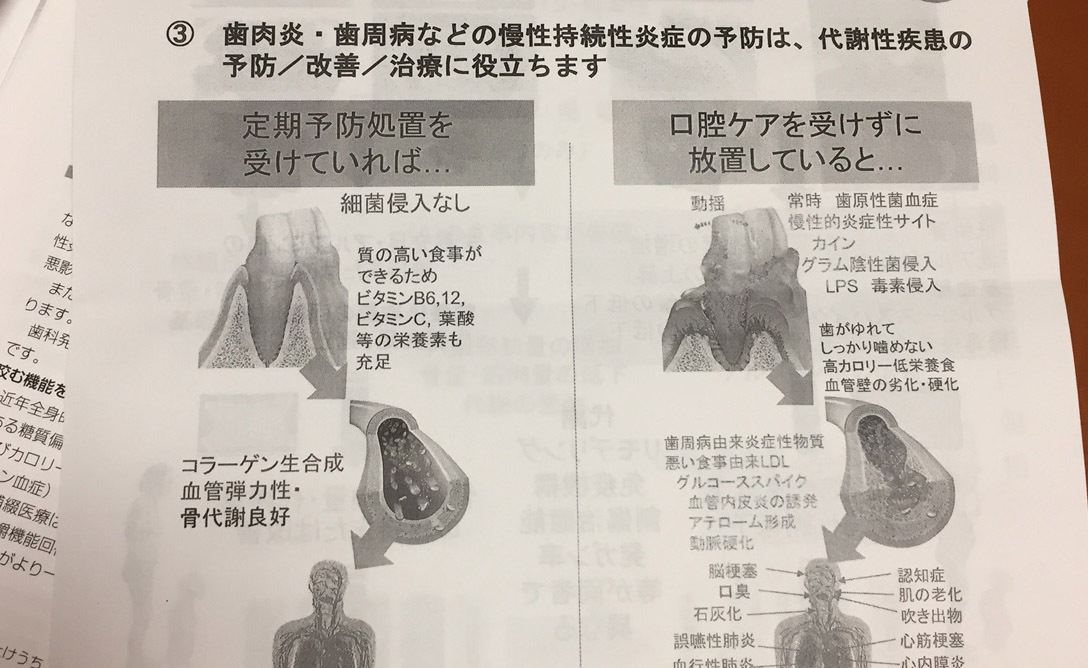
国際歯科学士会は世界中で秀でた国際的な歯科学組織です。この学士会の目的の一つは、公衆の健康と福祉のために歯科学の技術及び学術を国際的に促進することです。
今回の学会も歯周病に関する講演が中心でした。
食生活の偏りからくる口腔内の疾患、その疾患(歯周病)から始まる大きな病。
そのことを患者さんに伝え、防ぐことが私たちの役割です。
日本歯科医学会 平成28年10月21日〜23日

この学会は歯科学会の中でもとても大きな学会で、幅広い分野の専門家が多く集まるミーティングです。
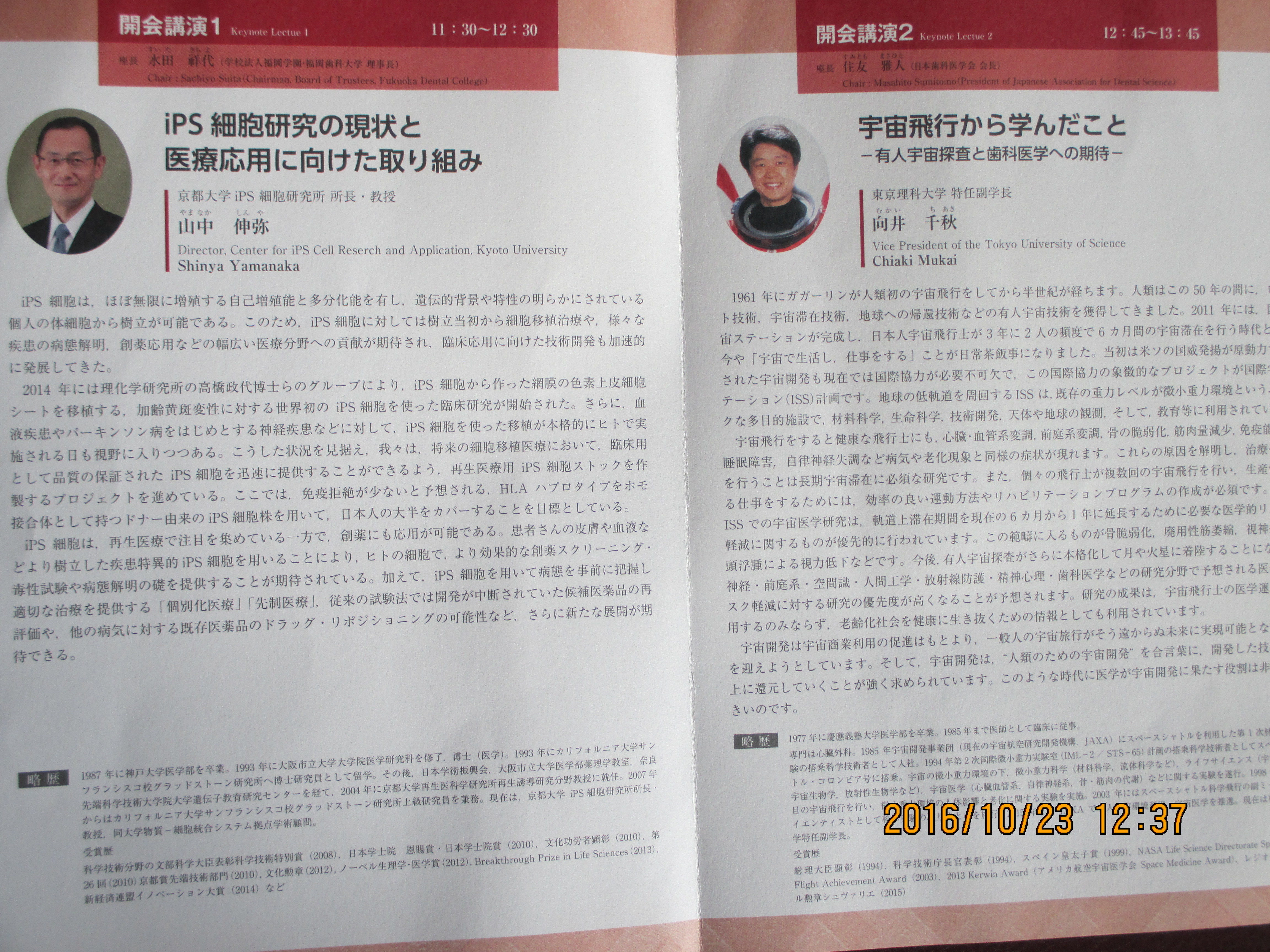
特別公演として山中伸弥教授、向井千秋さんの講演もありました。
関東労災病院地域連携講演会 平成28年9月12日
歯周病と糖尿病の関連など、今では医科・歯科での連携治療が一般的になっているため、このような講演が多く行われるようになりました。


春季 日本歯周病学会 鹿児島

今回の学会では鹿児島県で開催されました。
地震の復興支援も平行して行われ、多くの義援金が学会を通じて集まりました。
歯周病は歯を支える骨を溶かしたり、歯ぐきにダメージを与える病気です。
無くなった骨をiPS細胞を用いて再生する内容や移植に関する講演などがありました。
学会に参加することは最新の治療技術などの情報を収集できる大切なことです。
小嶋歯科医院では内科的に歯周病の治療をする新しい治療法など、常に最善の治療を提供できるような態勢をとっております。
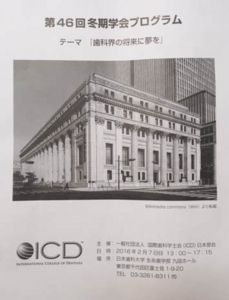
● 再生療法(エムドゲイン®など)をはじめ、これからの時代に向けて
進化をしている最先端の治療についての講演が目立ちました。
もちろんIPS細胞等の話題もさかんに出てきました。

今回の歯周病学会は千葉県の幕張メッセで開かれました。
年々参加者が増えている歯周病学会を見ると、国内における歯周病への関心の高まりを反映しているに他ならないと感じます。
● 歯肉の炎症が心臓や脳に与える影響について
● 骨が歯周病によって溶けていくメカニズム
● 噛み合わせと歯周病の関係
これだけではありませんが、上記に関する議題が印象深かったと感じています。
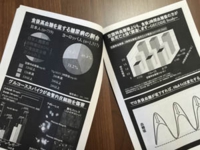
多くが罹患している生活習慣病です。今後も、治療以前の予防、平行した治療方法について多くの議論・研究が進んでいくと思われます。
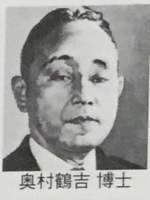
国際歯科学士会2015年2月15日:国際的に活動する大きな団体で、歯科の治療技術や知識の発展をグローバルに考える目的を持った団体です。その歴史は大変古く1920年に始まりOttofy博士と奥村博士によって広められた名誉のある会なのです。歯科によって人の健康を守り、より良い生活が出来ることを願い、今日まで発展してきました。臨床経験の少ないドクターは加入できない等の厳しい条件はありますが、日本国内においても活発な活動が行われています。

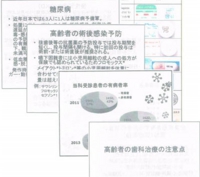
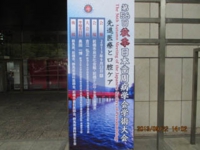
今回の学会では歯周病と糖尿病(生活習慣病)との関連性について多くの発表がありました。ポスターセッションでは、歯周病について真剣に取り組む先生方の発表があり、とても参考になります。
若い先生の演題も目に付き、日本における歯周病患者数の増加を裏付けていると感じました。
最近の歯周病学会では、歯周病と糖尿病、歯周病と心筋梗塞などの関連性について多くの講演が見られます。
歯科と医科との連携の大切さを感じます。


2013年春季歯周病学会ではこのような話題が取り上げられています。
1.超高齢社会に向けての歯周病治療
2.未来の歯科治療としての歯科再生療法
3.炎症性骨吸収のメカニズム
4.歯周病と糖尿病 など
高齢化社会へと突き進む中、歯周病に罹患されている患者数は年々増え続けています。高齢者だけではなく、歯周病患者の若年化もみられており、日本国内に置ける歯周病治療の重要さがとても大きくなっているように思われます。
私自身も地元港北区医師会の研究会で講演をしてまいりましたが、今後医科と歯科の交流がさらに進み、歯周病の治療、さらには糖尿病等の治療技術がさらなる発展を遂げる事を願っております。
下の写真は医師会での講演用スライドの1枚

お口の病気(虫歯や歯周病)は軽視されがちですが、重大な病気との関係が明らかになっている以上、我々歯科医師も真剣に取り組むことが大切です。

今回の学会ではメンテナンスを長期的に見た場合の効果や影響について多くの発表がありました。
ポスターセッションでは、歯周病について真剣に取り組む先生方の発表があり、とても参考になります。
若い先生の演題も目に付き、日本における歯周病患者数の増加を裏付けていると感じました。

アメリカだけではなくヨーロッパの国々からも多くの参加者があり、日本で開催される学会とはひと味違う、多くの情報が発信されます。
海外で開催される歯周病学会ではインターナショナルな講演やポスター発表が多く行われるため、学会参加は大変重要です。
今年の学会へは院長、副院長、允郎歯科医師が参加しました。


食習慣の変化に伴う歯周病患者の増大が背景に有るのでしょう。
当院では以前より行っているエムドゲイン療法やGTR療法がその代表例です。
当院には様々な地域から歯周病の患者さんが来院され、現在も治療をすすめておりますが、早期発見が一番大切です。
気がつかないうちに進行する歯周病の検査を一度受けられてはいかがでしょうか。
歯周病学会では一般的な講演やポスターによる発表が行われ治療に関する多くの情報を得る良い機会でもあります。



